
こんにちは しゅーなです!
中学生になると、学校でも英語弁論大会(スピーチコンテスト)の出場者の募集が行われるようになります。
中学生で英語弁論大会に出たい 出ることが決まった そんな人たちのために今日は私が英語弁論大会に出た時の体験をもとに練習方法を紹介していこうと思います。
でた大会について
私は、中学3年生の時に高円宮杯英語弁論大会(創作するやつ)に出場しました。
地方予選はこれと暗唱が同じ日に行われたのですが、出場者は創作の部の方が圧倒的に少なかった。
どっちにしよっかなーって迷ってるなら創作の部の方をおすすめします。
英作文ができなくても、日本語で内容さえ書き出せれば英訳は先生に手伝ってもらったり、アプリに手伝ってもらったりできるのでどうにかなるもんですよ(笑)
内容についてはこちらの別記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

練習のコツ
①暗記は早めに済ませる
暗記は原稿ができたらすぐに済ませてしまいましょう。暗記が済むと、とりあえず最後まで行けるから大丈夫 という気持ちになって精神的にも安心できたり、表現の練習や発音矯正に割く時間を増やすことができたりしてメリットしかないのでので最初に終わらせるのがベストです。
全部を一気に覚えようとはせず、意味のまとまりや文、段落ごとに区切って覚えていきましょう。また、文の構造なども頭にいれておくと覚えやすいかもしれません。
夜の寝る前と朝は必ず練習をするようにすると、割と簡単に暗記ができると思います。
また、家のトイレに原稿をはっておいて練習するのも効果的だと思います。トイレで暗記するのって本当に頭に入るのでおすすめです。(笑)
暗記方法についてはこちらの記事で詳しく紹介してしているのでよかったら参考にしてください。
お手本にできる音源を入手する
お手本にする音源は、原稿ができてすぐ、なるべく早く手に入れましょう。
一番手っ取り早いのは、学校のALTの先生に頼むことです。
私は、ALTの先生に頼んで原稿を読んでもらい、それを学校で一人一台配られるiPadで録音しました。
イントネーションやリダクションの仕方、発音など、やはりネイティブ物は違うので、何回も何回も繰り返し聞いて、まねて、完璧にコピーしましょう。
なるべく早くから行うことで、変な癖もつかず、楽にきれいな発音が身につきます。
練習は録画して後から反省
練習は、動画でとって後から見れるようにしておきましょう。
私は、録音よりも動画で残しておくことをおすすめします。ジェスチャーや視点の動きなどの発音以外で見られる、自分では見れないところも振り返ることができるからです。
自分ではゆっくり話したつもりなのに動画をきいたらめっちゃ早口だった
自分では視点をいろんな人にあてたりジェスチャーを大きくつけたりしたつもりだったのに後から見たら全然伝わらないくらい小さい動きだった
なんてこともよくあります。自分で感じていることと第三者目線からの自分ってやっぱり違うので。
だからこそ、せっかく練習したんだから後から反省して無駄にしないためにも動画で残しておきましょう。
いろんな人の前で練習する
練習は、英語の先生やALTの先生などの決まったちょっとの人の前だけでなく、学校のいろいろな先生の前だとか、学級の仲間の前だとか、大人数の前でも練習しておきましょう。
本番は、審査員だけでなくほかの出場者や引率の先生も見てますし、ステージも立派なので緊張します。なるべく緊張になれ、その中でも発表できるようにするために、少なくとも3回ほどは大人数の前、またはいつもと違う人の前で練習しておきましょう。
私は、学級で、文化祭で、校長先生などの先生の前で、練習をさせてもらいました。おかげで、本番もあせらずに落ち着いたいつも通りの発表ができたと思います。

本番くらいの広い場所でも練習する
大会にもよりますが、すくなくとも私が出た大会では、マイクが使えませんでした。早めに確認しておきましょう。当日にマイクが使えないことを知ったら絶対に焦ってしまうので。
広い会場でマイクなしなので、いつも家や教室で練習していた時の声量では全然足りません。
大きな声を出して会場の全員に届けられるようにするために、体育館や多目的室、廊下など、広いところでも練習しておきましょう。これは毎日しておくといいですね。
遠くの方に先生に行ってもらって、声がきちんと聞こえたか、ジェスチャーなどは見えたか、教えてもらってもGOOD👍
声がはっきりと聞こえた方が、もちろん審査員の評価もよくなりますよ。
ジェスチャーはあらかじめだいたい決めておく
ジェスチャーはその場のノリで行けるっしょ などと思ってしまいますが、本番は緊張してそこまで頭は回りません。原稿を思い出していくので精一杯になってしまうかもしれません。
だから、どこでなんのジェスチャーをするのかは大まかに決めておきましょう。
ずーっとなんかしらのジェスチャーをしている必要はありません。強調したい場所に、入れていきましょう。
視点の動かし方、声のボリューム、スピードも考える
ジェスチャーをずっとはしない代わりに、これらで表現していきます。
大事なところはゆっくり読んだり、声を大きくしたり。
みんなに問いかけるところでは、十分な時間を使って視線を全員に向けてみたり。
これだけでも全然違います。
また、これは自分が思っている以上に変化がついていないときが多いです。
撮った動画をフル活用して聞いている人がはっきりと感じ取れる変化を作っていきましょう。
最後に

最後までありがとうございました。
練習、頑張ってください!
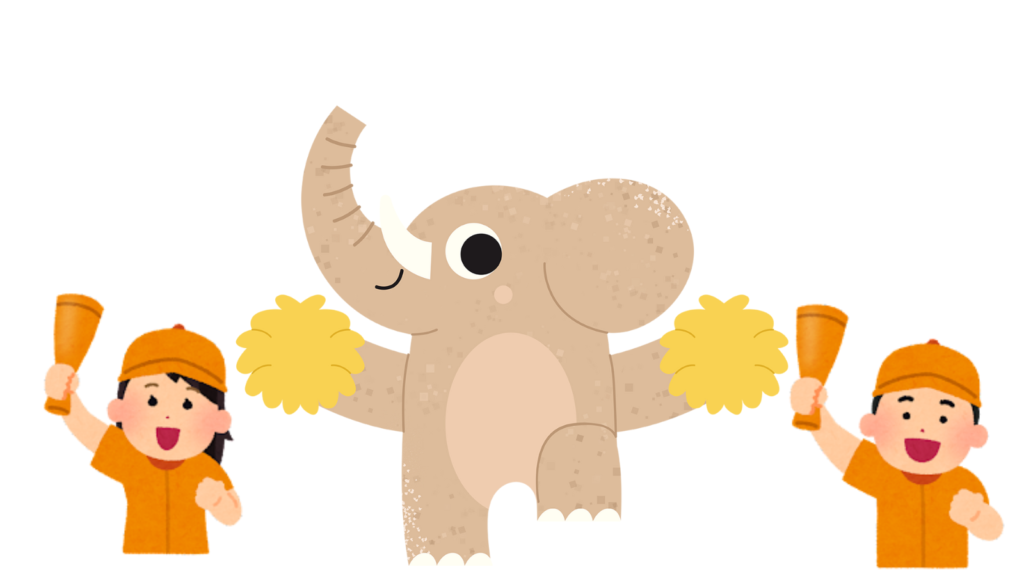


ふつーの女子高生 裁縫や英語などの大好きなものについて、留学中の日常や留学情報の発信をしています。





コメント